忙しい部署と暇な部署がある。
そのとき、管理職としてよくやるのが「人手を回す」ことです。
この記事では「人手のやりくり」という言葉を使いますが、組織運営では「人員融通」と言われることもあります。つまり、余っている人を他部署へ応援に出して問題を解決しようとするやり方です。
目次
人手のやりくり(人員融通)の副作用
本来、主導すべき店舗のメンバーが置いてけぼりになり、主体性を発揮しにくくなったり、協力体制が整わなくなったりしました。
正直、この時は少し気まずかったです。現場では笑顔で動いているのに、どこか冷めた目をしているスタッフもいて、
「これで良かったんだろうか」と電車の帰り道でずっと考え込んでいました。
人手のやりくりは応急処置にすぎない(人員融通の限界)
確かに「人を回せば解決」は楽です。
でも、それを繰り返していると、
- 各部署が「自分で考えなくても、なんとかなる」と思考停止になる
- 主体性や自律性が失われる
- 組織全体としては弱くなる
余談ですが、この経験のあと「他部署に人をお願いする」という提案が来ると、一度立ち止まって「本当にそれでいいのか?」と自分に問い直すようになりました。あの時のモヤモヤが、ちょっとしたストッパーになっています。
管理職に求められる役割
だからこそ、管理職は応急処置と構造改善を切り分ける視点を持たなければならないと感じました。
- そもそも、なぜ人手が余るのか?
- 逆になぜ、この部署は人が足りないのか?
- 主体部署とサポート部署の役割は明確になっているか?
- その配置は本当に人材の成長につながっているのか?
最後に問いかけたいこと
人手を回せば、今日の問題は解決するかもしれません。
でも、そのとき失っているものは本当にないでしょうか。
- 部署の自律性
- 個人の成長機会
- 組織としての持続的な強さ
管理職であるあなたは、目の前の「効率化」に頼っていませんか?
それとも、その先の「成長の仕組み」まで描けていますか?
今回の気づきの元になった現場体験の記事はこちらから読めます。
新しい企画でやりがちな「人手のやりくり」の落とし穴と学び
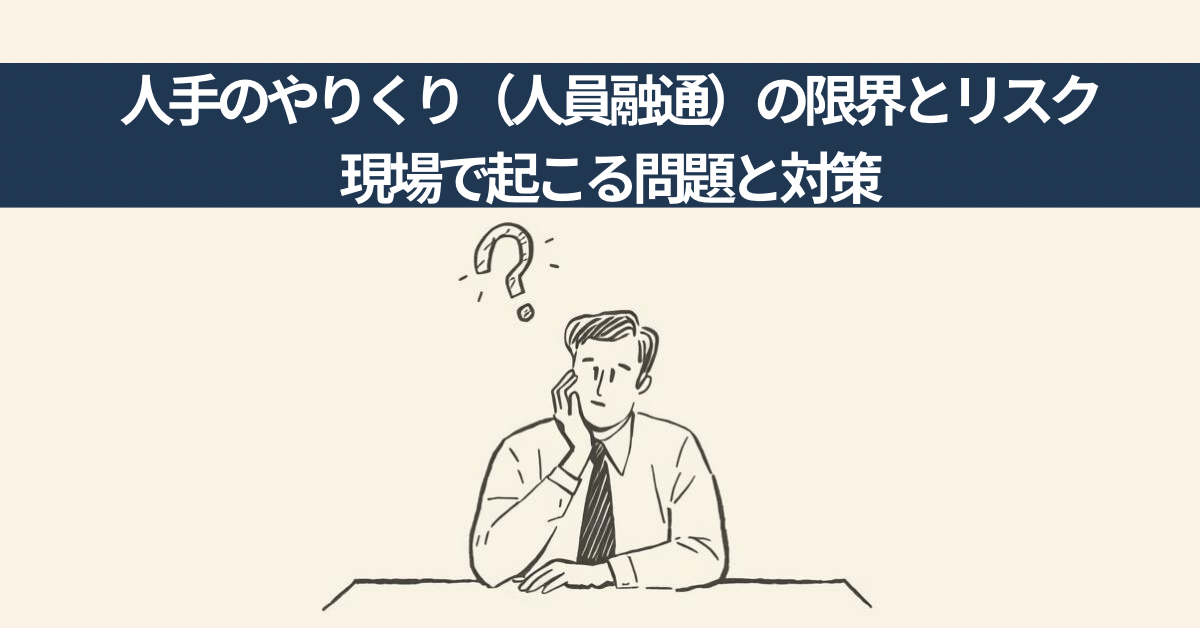
コメント